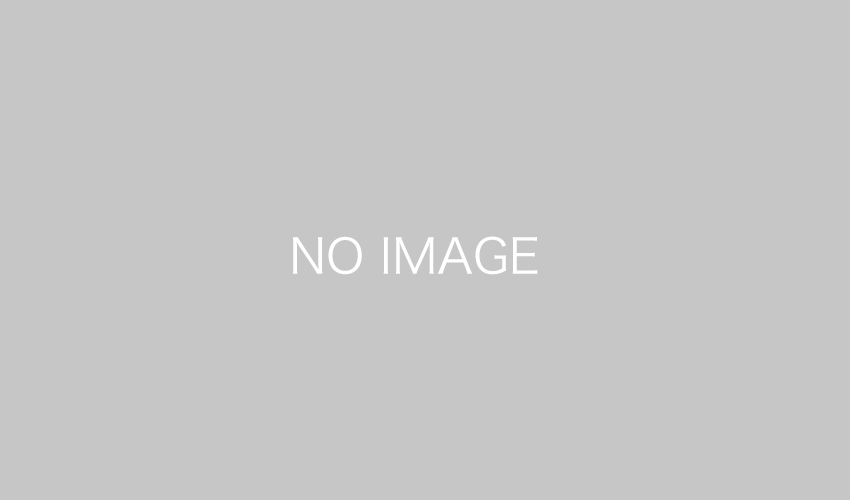エレベーターの安全性を保ち、機械トラブルや漏水被害を未然に防ぐために重要なのが「エレベーターピットの防水工事」です。
しかし防水と一口に言っても、使用される防水工法にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や効果が異なります。
本記事では、「浸透性防水」「ポリマーセメント系塗膜防水」「ケイ酸質系塗膜防水」「ビッグサンGR工法」など、主要な防水の種類を徹底比較。さらに「TACSS工法」や「IPH工法」といった特殊技術についても解説し、どの現場にどの防水法が最適なのかを明確に判断できる構成になっています。
- エレベーターピットにおける防水の重要性|水の侵入が引き起こすリスクと、防水工事の役割とは?
- エレベーターピット防水の主要な種類と特徴|現場の状況に応じた最適な工法を選ぶための基礎知識
- 浸透性防水とは?|コンクリート自体に防水性を持たせる工法の基本とメリット・注意点
- ポリマーセメント系塗膜防水とは?|柔軟性と強度を兼ね備えた定番防水材の魅力と採用シーン
- ケイ酸質系塗膜防水とは?|無機素材ならではの高密着性と耐久力が魅力。IタイプとPタイプの違いも解説
- ビッグサンGR工法とは?|湿った状態の施工面にも対応できる最新水性防水材の特徴
- その他の特殊防水工法:TACSS工法・IPH工法|独自の技術でピット内の過酷な環境に対応
- まとめ:防水種類の違いを正しく理解し、現場に合った最適な工法を選ぼう
エレベーターピットにおける防水の重要性|水の侵入が引き起こすリスクと、防水工事の役割とは?
コンクリートの劣化やエレベーターの故障を未然に防ぐため、防水処理は新築・改修問わず必須の作業
エレベーターピットは建物の最下部に位置し、常に地下水や雨水の侵入リスクにさらされています。
そのため、防水対策を怠ると次のような深刻な問題が発生する可能性があります。
-
エレベーター機械の故障:制御盤や昇降モーターに水がかかるとショートや誤作動の原因に。
-
サビ・腐食の進行:金属部品に錆びが広がることで寿命が短くなり、修繕費がかさむ。
-
異臭・カビの発生:湿気の滞留によりピット内にカビが生え、臭いや衛生問題につながる。
-
コンクリートの中性化・ひび割れ:水の侵入で中性化が進行し、建物自体の耐久性が低下。
このようなリスクを最小限に抑えるためには、目的に合った防水材・工法を選定し、適切な施工を行うことが不可欠です。
エレベーターピット防水の主要な種類と特徴|現場の状況に応じた最適な工法を選ぶための基礎知識
浸透性防水や塗膜防水など、それぞれの防水方法には「得意分野」と「制約条件」がある
以下に、エレベーターピットに使われる代表的な防水工法を一覧で比較します。
| 防水種類 | 特徴・適性 | 向いている状況 |
|---|---|---|
| 浸透性防水 | コンクリートに浸透して内部から水の侵入を防止 | ひび割れが少なく、構造体が健全なピットに最適 |
| ポリマーセメント系塗膜防水 | 高い追従性でひび割れにも対応しやすく、水槽などにも使われる | 既に微細なクラックがあるピットや、多用途な施設に最適 |
| ケイ酸質系塗膜防水 | 無機質な素材で構造体との相性が良く、施工後の密着性が高い | 中性化が進んでいるが健全なコンクリート面への塗布に適する |
| ビッグサンGR工法 | 湿潤面にも施工可能な高性能水系防水材 | 湿度の高い地下ピットや、乾燥時間を短くしたい現場向け |
この表からも分かるように、防水方法ごとに得意な条件や施工向きの環境が異なります。
それぞれの方法について、さらに詳しく解説していきましょう。
浸透性防水とは?|コンクリート自体に防水性を持たせる工法の基本とメリット・注意点
劣化の進んでいない構造体におすすめ。防水材が深く浸透することで長期的に水をシャットアウト
浸透性防水は、コンクリート表面に防水材を塗布し、毛細管現象を利用して内部へと浸透させる防水工法です。
これにより、コンクリート自体が水を通しにくくなり、長期間にわたって水の浸入を防ぐ効果が期待できます。
メリット
-
コンクリートの構造を変えず、目立たない仕上がり
-
長期にわたり効果が持続
-
材料費が比較的安価
注意点
-
ひび割れが進んだ部分には効果が薄い
-
内部から水が湧き出すようなピットには不向き
新築時や、軽度な水の侵入があるだけのケースに向いています。
ポリマーセメント系塗膜防水とは?|柔軟性と強度を兼ね備えた定番防水材の魅力と採用シーン
ひび割れ追従性に優れ、幅広い施設・用途に対応できる高汎用性の塗膜型防水工法
ポリマーセメント系塗膜防水は、セメントにポリマー(樹脂)を混ぜた材料を使用する防水工法です。
乾燥後に弾力性のある塗膜が形成され、微細なひび割れにも柔軟に追従できるため、構造体の動きにも強く対応できます。
メリット
-
躯体のひび割れに追従しやすい
-
水槽や地下構造にも使われる強度
-
仕上げが滑らかで美観も良い
注意点
-
施工には技術と手間がかかる
-
乾燥までに一定の時間が必要
既存のピット改修時に多く採用される、バランスの良い防水方法です。
ケイ酸質系塗膜防水とは?|無機素材ならではの高密着性と耐久力が魅力。IタイプとPタイプの違いも解説
中性化防止と強力な密着性を兼ね備えた防水方法で、湿潤面施工にも対応できる工法
ケイ酸質系塗膜防水は、ケイ酸ナトリウムなどの無機成分を含む材料を使用することで、コンクリートとの密着力を高め、防水効果を長く持続させる工法です。
施工方法には、「Iタイプ(セメントと水)」「Pタイプ(樹脂を加えた粉体と水)」の2種類があります。
IタイプとPタイプの違い
| タイプ | 構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| Iタイプ | 既調合粉体+水のみ | 無機質のため長寿命、乾燥時間が短め |
| Pタイプ | 粉体+エマルジョン or 再乳化樹脂+水 | 柔軟性があり施工しやすく、ピンホールの心配が少ない |
既存のコンクリート面に高密着で塗布したい場合や、中性化対策を取り入れたい場合に有効な選択肢です。
ビッグサンGR工法とは?|湿った状態の施工面にも対応できる最新水性防水材の特徴
雨水や地下水の多い現場で力を発揮する高性能防水材。短工期・環境対応型の優秀な選択肢
ビッグサンGR工法は、オール水系(有機溶剤を使用しない)の防水材料を使うことで、安全かつ環境に優しい施工が可能な防水工法です。
施工面が湿っていても使えるため、ピット内部が完全に乾ききらない現場や、早期復旧が求められる場所に適しています。
メリット
-
湿潤状態でも施工可能
-
施工後の収縮が少なく、塗膜安定性が高い
-
環境対応型で安全性が高い
注意点
-
雨中施工は不可(湿潤と濡れている状態は別)
-
事前の適合確認が必要
その他の特殊防水工法:TACSS工法・IPH工法|独自の技術でピット内の過酷な環境に対応
重度の劣化や内部漏水に対応できる、高度な技術を用いた特殊防水工法の概要
通常の塗膜防水や浸透系防水では対応が難しい現場においては、以下のような特殊工法が採用されることがあります。
TACSS工法
-
特殊な樹脂材をコンクリート構造体内部に浸透・固化させる工法
-
構造体の強化と同時に防水性を高める
-
浸水が激しい現場や地盤に問題があるピットに有効
IPH工法
-
加圧状態でエポキシ樹脂を構造体に注入し、防水と補修を一体化する工法
-
ひび割れが進行している、または内部から水が湧き出しているような現場に向く
これらは通常の防水と比べて費用は高くなりますが、トラブルの再発リスクを極めて低く抑えることが可能です。
まとめ:防水種類の違いを正しく理解し、現場に合った最適な工法を選ぼう
エレベーターピットの防水工法は、**「どんな漏水に悩まされているか」「ピットの状態はどうか」「施工条件やコストは?」**によって最適な選択が大きく変わります。
表面的には似たような塗膜でも、成分や用途、適した環境が異なるため、一律で「これが最適」と言える防水工法は存在しません。
まずは現地調査によってピットの状態を正確に把握し、そのうえで「浸透性でいけるのか」「追従性が必要か」「湿潤施工か乾燥必須か」といった観点から最適な工法を選びましょう。
また、施工実績豊富な業者に相談することで、工法選定から施工、アフターまで安心して任せることが可能になります。
エレベーターピットの防水は、「安全性」と「将来のコスト」の両面で非常に重要な投資です。
現場の状況に応じて、最適な防水対策を講じ、エレベーターの安全運用を守りましょう。